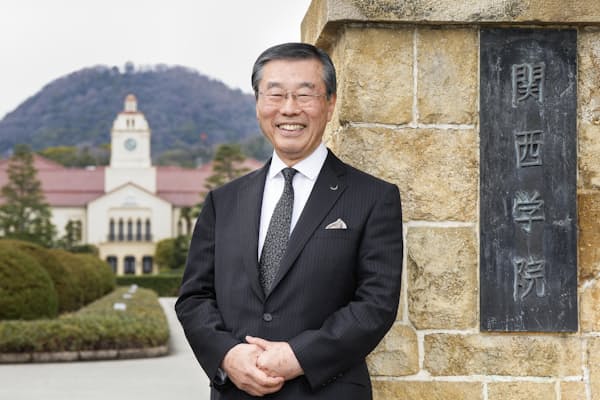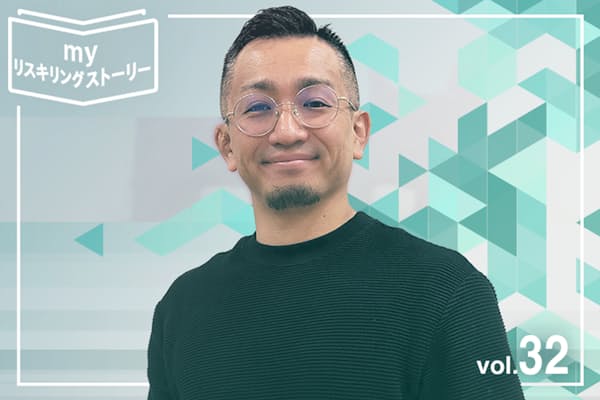「日本らしさ」強みに~ボスコン日本代表に聞く(2)
日本企業は本当に「遅れている」のか?

――「デジタル」への対応という点で言いますと、出遅れ感を持っている日本企業は多いように思います。
人工知能(AI)も含め、デジタル分野に関する技術で言いますと、たしかに遅れているかもしれません。しかし、希望が全くないわけではないでしょう。
ある日本企業の方から、こんな話を伺ったことがあります。その方が、アメリカのAI領域におけるトップクラスの研究者に「日本はこれから、どうやってデジタルの分野で欧米企業に追いついていったらいいのか」と質問したところ、その研究者はこう答えたそうです。「その部分は彼らにリードさせておけばいい」と。
これはなにも「デジタルは諦めろ」という意味ではなくて、もっと自分たちの強みに着目しなさい、という意味でした。では、その強みは何かと言いますと、ひとつは「マスプロダクション」だと思います。
アメリカの製造業は生産拠点を中国に移すなど極端なファブレス(工場無し)化を進めた結果、マスプロダクションをしていくための実験場さえない状態です。日本の場合は幸か不幸か、ものづくりを捨てきれず、国内に比較的多くの工場を残しています。今後、このものづくりの能力が大きな強みへと変わっていく可能性はあります。
現在起きているデジタル化の波を「IoT(モノのインターネット化)」と呼ぶか、「インダストリー4.0」と呼ぶかは別として、その本質は何かと言えば「産業のデジタル化」です。ということはつまり、「デジタル」と「ものづくり」のどちらか一方だけを持っていても、それをリードする企業にはなれず、産業基盤であるものづくり力とデジタル化への対応力、この2つの組み合わせによって「強み」を最大化できた企業が次代をリードしていくフェーズに入った、ということです。
「新しいこと」だけでは勝てない
デジタルマーケティングの世界では「個人」との接点をどう結ぶか、がとても重要です。これまでの伝統的なメディアの世界とでは、ユーザーエクスペリエンス(利用体験)のつくり方がまったく違う。そこにいち早く気づいて対応できるかどうかで、最終的に獲得できるお客様の数も大きく変わってきます。
これは既存の企業にとっては大きな脅威かもしれませんが、見方によっては大きなチャンスにもなります。なぜならば、先ほど申し上げたように、デジタルが普及すればするほど、それ以前に蓄積した経験や人材の質など、目に見えない知的財産の部分がビジネスの勝敗を左右するようになっていくからです。
全体として日本の大企業に欠けているのも、ここの部分の戦略です。戦略とはそもそも、企業が現在持っている資産と新しい資産を組み合わせて、どのような優位性がつくり出せるのかを考えること。もしも、これまでの蓄積がすべて無駄であり、新しいアセットを持った人たちだけが勝てるのならば、ベンチャーの方が有利に決まっています。しかし、現実はそう単純ではありません。
前回説明したように、コンサルティング業界で今起きていることが、その最もわかりやすい証明でしょう。投資余力と経験の蓄積がある者だけが生き残っていく。「古くからある強み」と「新しさ」をどう結びつけるのか、が大きな鍵を握る時代になってきたということです。
――その場合、日本人あるいは日本企業が高めていかなければならない能力は何だと思いますか。
CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)のような、自社にない能力の活用や、M&Aを含めたアライアンスを成功させていく力が必要になると思います。
我々の調査によれば、M&A後の1年間で、企業価値を相対的に高めることのできた企業はグローバルで見ても、約半分しかありません。M&Aをめったにやらない企業ならば、この確率はもっと低くなりますから、日本企業がM&Aによってシナジーを生み出すことがいかに難しいかはおよそ想像がつくと思います。
ただし、この点に関しても、日本らしいやり方で成功事例を積み上げ、ノウハウ化できれば、かつて世界から尊敬を集めた「日本的経営」のように価値のあるモデルが出来上がるはず、という希望を持っています。
企業理念を世界共通の言葉に
欧米企業のM&A後の統合はある意味、非常にオーソドックスで、最も生産性の高いプラットフォームにすべてのものを合わせていく、というやり方です。相対的に劣っている部分をベストなところに合わせることで大きなシナジーを生み、稼ぐ力をつけていく。このコストシナジーの部分で、欧米企業は明らかに日本企業よりも多くのノウハウを蓄積していますが、もしも、もっと日本的なやり方で、生まれも育ちもまったく違う企業同士が換骨奪胎しながら一体として新しいモデルをつくっていけるのだとしたら、それはこの分野における一種の画期的な発明になります。
その点で興味深いのは、確かな理念とビジョンを掲げた日本企業が海外企業を買収し、統合しようとした場合、比較的うまくいくケースが多いという事実です。理念やビジョンなんてわざわざ口に出して唱えるのは恥ずかしい、そんなもの言わなくてもわかっているはず、あるいは言っても一銭にもならないじゃないか、と思う方がいるかもしれませんが、これが案外、効きます。
欧米人にとって、企業理念は「コベナンツ」のようなもの。コベナンツは融資の特約条項の意味でも使われる言葉ですが、本来は「神との誓約」を意味します。同じように、多くの日本企業には、最後に立ち返るべき「背骨」と言えるような理念があるはず。それを暗黙のうちに分かりあうのではなく、異文化の人たちが理解できるところまで言語化していくことで、日本企業に対する尊敬と求心力が生まれます。
企業理念には、その企業が持つ歴史やそもそもの成り立ち、存在意義などが詰まっています。工場を減らし、人員整理をしながらシナジーを生み出すのはハードな部分の統合ですが、生まれも育ちも違う人間同士が一体となり、ベクトルを合わせながら、どうやって新しいモノやサービスを生み出していけるかを考えるのは、ソフトな部分の統合です。
ソフトな統合に必要なのは、他者の気持ちを理解する「共感力」であり、お互いを尊敬し合う心でしょう。この部分において、日本人はもともと優れた感覚を持っていたはず。ですから、もう一度、創業の原点に立ち返り、「日本的経営」の持つ強みを土台にして、それをさらに進化させた日本らしいグローバル経営のあり方を模索していってもいいのではないか、と思っています。
(聞き手:日経Bizアカデミー編集長 代慶達也、ジャーナリスト 曲沼美恵/構成:曲沼美恵)
1961年生まれ、愛知県出身。東京工業大学工学部卒業、慶応義塾大学経営学修士(MBA)。日本交通公社(JTB)勤務を経て、1994年、BCG入社。2006~2013年、BCGジャパン・システム オフィス・アドミニストレーター(統括責任者)。2007年、シニア・パートナー&マネージング・ディレクター就任。2014年、BCGクライアントチームアジア・パシフィック地区チェア、2016年1月から現職。
[日経Bizアカデミー 2016年1月22日付]